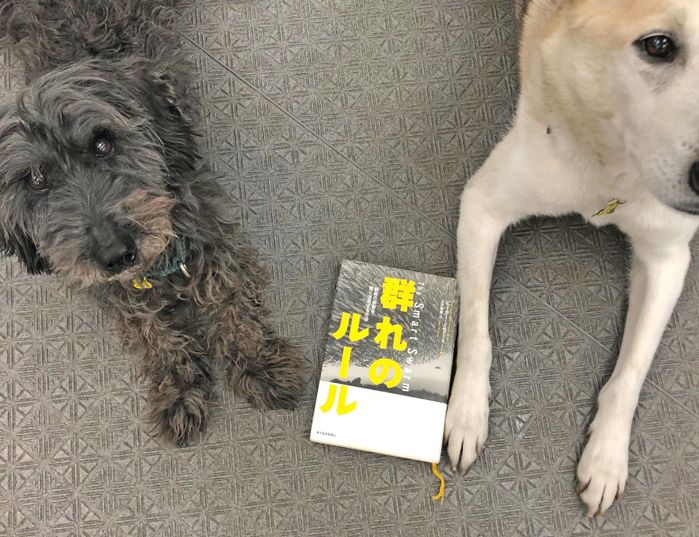犬が好き
UP DATE
犬は順位づけなんてしない|連載・西川文二の「犬ってホントは」vol.23
今回は犬同士の順位づけのお話。犬たちのなかでは「強い・弱い」の力関係で順位づけをしているように見えますが、本当はしていないのだとか。ちなみに、犬は人間に対しても同様で、「いつも言うことを聞く人を一番上に見ている」という順位づけもしていないのだそう。実際はどうなのでしょうか?(編集部)
そう評されるのはアリ塚です。
内部構造は一定湿度が保たれるような空調システムがそこに存在する、という見事なものだそう。
ムクドリの群れや魚群の動きに関しては、人間なら誰かが統率、指示を出さなければとても描けないであろう、といわれる。
なぜそのような構造物がアリに作れるのか?
なぜ、ムクドリの群れや魚群は、あのような動きができるのか?
(大丈夫です、今回も犬の話で落ち着きますので)
個々は単純な原則に基づく行動をとっているだけ
魚やムクドリは、「近くの個体と近づきすぎたら距離を取る、近くの個体と速度と方向を合わせる、より多くの個体のいる方向へ向かう」、という行動の原則に従って動いているだけ。
こうした仮説が生まれ、それが確かにそうなると確認されたのは、動物の行動研究にコンピューター・シミュレーションが用いられるようになってからのことです。
動物たちは、環境などから得られる情報に応じて、個々が単純な原則に基づく行動を、それぞれの個体が行っているだけ。誰かの指示に基づく動きをしているわけでもない、全体像を決して理解しているわけではない(できないし、する必要もない)。そういうことなのです。
絶対的な順位など存在し得ない
「犬は順位をつくる」は、真実か否か。
A、B、C、D、Eという5頭の犬がいるとします。
順位は「>」記号を用いて記せます。
そして、D>E>A>C>B ならば、Aは上から3番目と下から3番目などと、順位がわかるわけです。でもこれって、全体を把握できることが前提の話です。
単純な原則に基づく個々の行動の結果が全体を織りなしているのであれば、まずは単純な原則に基づく個々の行動から見ていくことです。
例えば、AとBにそれそれが手に入れたいと思う価値ある何か(リソースといいます)を、1つ(ここではおもちゃにしましょう)を与えるとします。争いを避けるためには、どちらかの犬が他の犬にリソースを譲る必要があります。
AがそのリソースをBに譲るのであれば、A<Bと「>」記号を用いて記すことができます。
ただ、同じおもちゃでも状況によって、または種類によって、A<BがA>Bに入れ替わったり、おもちゃ全般はA<Bだけども、ガムに関してはA>Bとなったり、する。
ここにC、D、Eが加われば、Aが行うのはA<B、A>C、A<D、A>E、BはBでB>A、B>C、B<D、B>E、さらにCはCでDはDでEはE。それも単純ではなく、状況によって、B<DがB>Dになったりする。
たった5頭でもその順列パターンはかなりの数になってしまいます。
そうなのです、そもそも絶対的な順位づけなど、できない話なのです。
人間のことを、上に見たり下に見たりなどもしない
それに関しても、お話をしましょう。
リソースは常に、飼い主や家族から与えられています。
となれば、「争いを避けるためにどちらかがリソースを譲る」という「>」記号のような行動の原則を、犬の人間との関係においては当てはめることは、適切ではありません。
では、人間との関係においては、犬はどういった原則に基づいて行動を起こしているのか。
それは、こういうときには「こういう行動をすればいいことが起きる」、こういうときには「こういう行動をすれば嫌なことが起きる」、こういうときには「こういう行動をすればいいことがなくなる」、こういうときには「こういう行動をすれば嫌なことがなくなる」。
これらの行動の原則を過去の経験から学んでいて、都度その原則に基づきその犬にとって最適な行動を起こしている、ということなのです。
一度、順位づけ云々という色眼鏡は外して、こうした視点で犬たちの行動を観察してみてくださいな。
今までと異なる、犬たちの真の姿がそこに見て取れるはずですから。
写真/Can ! Do ! Pet Dog School提供
https://cando4115.com/index.html
西川文二氏 プロフィール
UP DATE