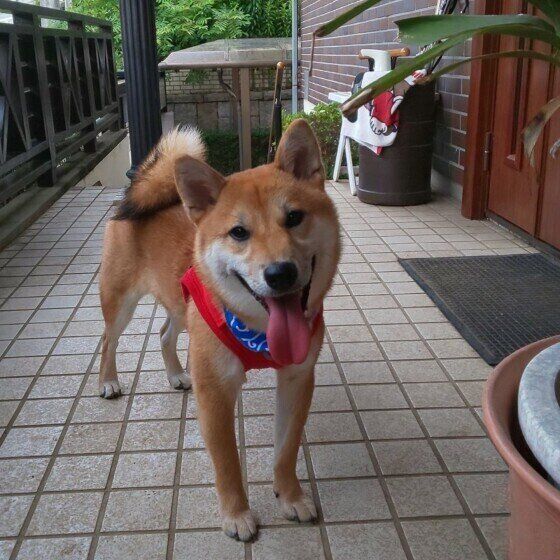犬と暮らす
UP DATE
【獣医師監修】犬の膀胱炎とは 原因・症状から治療・食事やお手入れで気を付けること
愛犬のオシッコに異変を感じたら、膀胱炎かもしれません。どのような原因で膀胱炎を発症し、発症するとオシッコや排尿時の様子にどんな異変があらわれるのでしょうか。膀胱炎になったときの治療や予防法、お世話の注意点も交えて、犬の膀胱炎を解説します。

いぬのきもち獣医師相談室
犬の膀胱炎の種類と原因
細菌性膀胱炎
結石による膀胱炎
そのほかの原因による膀胱炎
- ストレスを抱えている
- 外傷や膀胱腫瘍がある
- 神経の異常や解剖学的な奇形により膀胱が正常に収縮せず尿が残留する
- 糖尿病などの基礎疾患がある
- 免疫を抑える薬を使った治療中である
膀胱炎の症状・サイン
オシッコの色・ニオイ・量
また正常なオシッコは人と同じアンモニア臭がかすかにする程度ですが、健康ではないオシッコは鼻をつくきついニオイや生臭いニオイなどいつもと違うニオイがします。少量のオシッコを1日に何回もする場合も、膀胱炎の可能性がありますので、病院を受診してください。
排尿時の様子
- いきむ様子が見られる
- 排尿姿勢の変化
- 痛そうにしている
- 1回のトイレ時間が長い
- まったく出ない
- オシッコの切れが悪い
- 何度もトイレに行く
そのほかの様子
犬の膀胱炎の診断と治療
膀胱炎の診断法
膀胱炎の治療法
結石や結晶が原因で発症する膀胱炎は食事療法で治療を行うことが多いですが、医療用のフードで溶けない結石がある場合などは、手術で取り除くこともあるでしょう。治療により症状が改善された場合でも、再発防止のために結石ができにくいフードを食べ続けていく必要がでてきます。
犬の膀胱炎の予防法
十分な量の水を飲ませる
愛犬がいつでも水を飲めるよう、朝・昼・夕方・寝る前に水の残量を確認して、古くなった水は取り換えることを習慣に。室内の水飲み場を増やしたり、ボウルの高さを変えたり、水に愛犬好みのニオイや味をつけたりすると、積極的な水分補給が促せるでしょう。
そのほかにはゴハンをウエットフードに替える、ドライフードをふやかして与えるなどすると、食事しながら水分補給することができます。
愛犬が飲んだ水の量を把握する必要があるので、直接ボウルに注ぐのではなく、ペットボトルにうつしてから注ぐようにすると、減り具合からだいたいの飲水量が把握できるでしょう。犬が1日に飲む水の量の目安は、下記を参考にしてください。
犬が1日に飲む水の量
- 体重20kg未満の小型犬・中型犬・・・体重1kgあたり30~50ml
- 体重20kg以上の大型犬・・・体重1kgあたり50~70ml
オシッコを我慢させない
- いつもいる場所からトイレが遠い
- トイレが汚れている
- 屋外でしかオシッコしない
愛犬が好きなときにトイレへ行けるよう、いつでも行ける場所にトイレを設置し、トイレシーツは1回使うごとに交換しましょう。留守番をさせる際は、複数のトイレを用意してあげるとベストです。
散歩中にしか排泄しない犬の場合は、室内のトイレ習慣も身に付けさせたいです。トイレへ連れて行き、オシッコができたらご褒美をあげて訓練しましょう。
しっかりと散歩をさせる
- 散歩が不足している自覚がある
- 冬になると散歩を減らしている
- 雨の日は散歩を休みがち
犬の膀胱炎に関するお悩みQ&A
膀胱炎が治らない・再発するのはなぜ?
また、治療に時間がかかる場合、抗生物質の長期投与への不安から飼い主さんが自己判断で投薬を中止してしまうケースが見られますが、これも再発の原因になります。必ず獣医師の指示通りに投薬をするようにしましょう。
なお、基礎疾患などにより引き起こされる膀胱炎は完治することが難しいです。膀胱炎を治すのではなく、できるだけ膀胱炎にならないようにコントロールすることを目指す治療がほとんどです。
どんな犬がかかりやすいの?
また、膀胱に結石ができやすいなどの遺伝的な体質から、ダルメシアン、ミニチュア・シュナウザー、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、ミニチュア・ダックスフンド、パグ、シー・ズーは特に膀胱炎に注意が必要といわれています。
排尿・排便後のケアを変えるべき?
ただ、下痢をした場合には、ウエットティッシュや濡らしたタオルできれいにお尻まわりを拭いてあげましょう。その際は陰部には触れず、肛門の周囲だけを注意しながら拭いてあげてください。
長毛で汚れが気になる場合
シャワーの回数を増やした方がいい?
お尻まわりの常在菌が原因になるとはいえ、洗い流すことで効果があるという根拠もありませんので、ふだんと変わらないお手入れを行っていれば問題ないでしょう。
食事内容を見直した方がいい?
例えばストラバイト結晶(リン酸アンモニウムマグネシウム結晶)などを伴う膀胱炎の場合には、病院から処方される療法食を与えて結晶を溶かす治療となります。療法食以外のものはおやつなども基本的に禁止されます。にぼしなどはストラバイトの原因になる成分を含むため、与えないようにしてください。ストラバイト結晶の治療中にも与えることができるおやつなども、病院によっては扱っていますので、かかりつけの先生に相談してみてください。
「いぬのきもち」2017年5月号『健康?病気?4つのポイントでわかる!愛犬のオシッコチェック やってみよう』
「いぬのきもち」2020年1月号『冬も上手に水分補給しよう!水を飲む量が減ると起こる不調・病気』
「いぬのきもち」2021年2月号『何かヘンかも!?気がかりだったアレコレに答えます!トイレのお悩みまるごと解決!(健康編)』
監修/いぬのきもち相談室獣医師
文/こさきはな
※写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
UP DATE