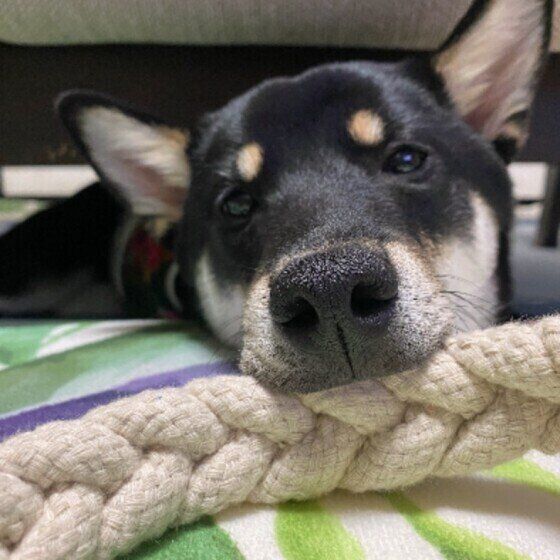犬と暮らす
UP DATE
【獣医師監修】犬にしいたけを与えるときは注意が必要。与えるメリットとデメリットを解説
しいたけは、犬が食べても大丈夫です。野生には生えていないキノコであるため「誤って与えてしまう」「誤って摂取してしまう」という心配もなく、安心な食材であるといえます。便通をよくする食物繊維や悪玉コレステロールを下げる働きが認められるエリタデニン、丈夫な歯や骨を作るのに必要なビタミンDなど、犬の体によい栄養素を豊富に含んでいます。ただし、過剰摂取は下痢や嘔吐などの原因になるので注意が必要です。

佐野 忠士 先生
酪農学園大学獣医学群獣医学類准教授
酪農学園大学附属動物医療センター 集中治療科診療科長
日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)卒業
東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻博士課程修了
北里大学獣医畜産学部および同大学獣医学部勤務
日本大学生物資源科学部獣医学科勤務
●資格:獣医師/博士(獣医学)/世界的獣医心肺蘇生ガイドラインインストラクター(RECOVER インストラクター)/CCRP
●所属:日本獣医麻酔外科学会/日本獣医学会/日本獣医師会/日本動物リハビリテーション学会/動物臨床医学研究所/日本麻酔科学会/日本臨床モニター学会
●主な診療科目:麻酔科/集中治療科
●書籍:『asBOOKS チームで取り組む獣医師動物看護師のためのICU管理超入門』/『as BOOKS チームで取り組む獣医師・動物看護師のための輸液超入門』/『動物看護師のための麻酔超入門・改訂版』 など多数
犬にしいたけを与えるときは加熱してから。ビタミンDの過剰摂取には要注意
食物繊維やビタミンDなど体によい影響を与える成分が豊富で、しかも低カロリー。そんなしいたけは、犬の体にとってもメリットの多い食べ物のひとつです。含まれる栄養素のなかで、とくに注目すべき成分としては、食物繊維とエリタデニン、ビタミンD、カリウムなどが挙げられます。
ただし、それらの体によい成分も過剰に摂取すると健康を害することにもなるので、与える量や与え方には気をつける必要があります。
しいたけのおもな栄養素|生と乾燥では成分に大きな違いあり
| エネルギー | 25kal |
|---|---|
| 水分 | 89.6g |
| タンパク質 | 3.1g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| 灰分(無機質) | 0.6g |
しいたけに含まれるおもな栄養素(乾) ※数値は可食部100gに含まれる成分
| エネルギー | 258kal |
|---|---|
| 水分 | 9.1g |
| タンパク質 | 21.2g |
| 脂質 | 21.2g |
| 炭水化物 | 62.5g |
| 灰分(無機質) | 4.4g |
文部科学省「食品データベース」https://fooddb.mext.go.jp/index.plより参照
犬がしいたけを食べるメリット|低カロリーで食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富
食物繊維|腸内環境の改善と便秘の解消
一方「不溶性食物繊維」は、腸の中で水分を吸って膨らみ、便のカサを増して腸の運動を促して、排便をスムーズにするほか、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えてくれます。
しいたけには、その両方の食物繊維が含まれていますが、とくに不溶性食物繊維が多く、ふだんから便秘気味の犬にはメリットのある食べ物といえそうです。
エリタデニン|悪玉コレステロールを下げる
カリウム|余分な塩分の排出と血圧調整
ビタミンD|丈夫な骨や歯を作る
生しいたけにもエルゴステロールは含まれていますが、天日干しにすることでエルゴステロールがビタミンDに変化するため、乾燥しいたけは生に比べてビタミンDの含有量は約56倍にのぼります。
βグルカン|免疫活性、血糖値を抑える
犬がしいたけを食べることで、同様の抗腫瘍効が期待できるかどうかは明らかではありませんが、犬にβグルカンを給与することで、免疫細胞が活性化したという海外の研究報告もあるようです。
さらに、βグルカンには食後の血糖値の上昇を抑える働きがあるのではと考えられています。
犬がしいたけを食べるデメリット|過剰摂取で便秘に。持病のある場合も要注意
食物繊維|不溶性食物繊維の過剰摂取で排便が困難に
カリウム|腎臓病や心機能低下の場合は要注意
とくに、腎臓病を患っている場合は、カリウムの排出がうまくできないので、腎機能が低下している犬にはしいたけは与えない、または与える前に必ず獣医師に相談してください。
また、心機能が低下している犬の場合も与える前に必ず獣医師に相談しましょう。
ビタミンD|結石症の場合は要注意
タンパク質に免疫機能が過剰反応する場合も
犬にしいたけを与えるときの注意ポイント|石づきは取り除き、加熱して与えよう
与えてよい部位
与えるときの適量
しいたけ(生)
| 犬の体重目安 | 1日あたりの摂取可能目安 |
|---|---|
| 小型(2~5kg) | 75g~150g(3個~5.5個) |
| 中型(6~15kg) | 172g~342g(6.5個~13個) |
| 大型(20~50kg) | 424g~842g(16個~32個) |
しいたけ(乾)
| 犬の体重目安 | 1日あたりの摂取可能目安 |
|---|---|
| 小型(2~5kg) | 7g~14g(1個~2個) |
| 中型(6~15kg) | 17g~33g(3個~4個) |
| 大型(20~50kg) | 41g~82g(5個~10個) |
※数値は、避妊・去勢済みの犬で体重相応のおやつ(1日の総摂取カロリー目安の1割)として算出
調理方法
また、干ししいたけは細かく刻んでもそのままでは固く、犬の口中や喉を傷つけてしまうかもしれません。必ず水で戻して柔らかくしてから軸と石づきを切り取り、傘の部分を刻んで与えます。干ししいたけを戻した汁には、しいたけの栄養分が流れ出ているので、ドライフードをふやかすのに使っても。しいたけのよい香りが、愛犬の食欲をそそる効果も期待できるでしょう。
低カロリーでヘルシーなしいたけ。過剰摂取に気をつけて上手に活用を
文/村田典子
※一部写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
UP DATE