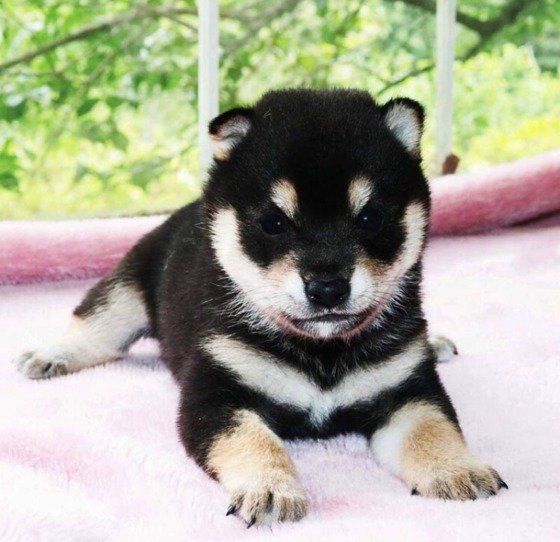犬と暮らす
UP DATE
【獣医師監修】豆柴ってどんな犬?柴犬とはどこが違うの?
豆柴と柴の違いは?
つまり豆柴はあくまで柴という括りであり、小さいサイズの子が「豆柴」と呼ばれているだけなのです。
豆柴は1955年ごろに誕生したといわれていますが、そのルーツははっきりしていません。
「日本犬保存会」や「ジャパンケネルクラブ(JKC)」などの団体は、豆柴を犬種として認めないスタンスを貫いています。そのため、JKCが発行する血統書には「豆柴」という表記はなく、「柴」と記載されます。
豆柴の性格・毛色は?
豆柴の性格は?
柴は自立心が強いといわれ、誰にでもフレンドリーに接するわけではありません。しかし飼い主さんに対しては、深い愛情を示し非常に従順です。柴が「忠犬」と呼ばれるのはそのためなのですね。
柴は飼い主さんにも常にベタベタするのではなく、一定の距離を保ちたがる傾向があります。そのため「愛犬といつもくっついていたい」という飼い主さんには物足りないかもしれません。その一方でそばに寄ってきて甘えたがるときもあり、「ツンデレ」な犬といわれることも。
また柴は頑固な性格でもあり、「絶対にこの場所で寝る」「トイレは外がいい」などと、強いこだわりも見られます。
※性格には個体差があるので、目安としてとらえてくださいね。
豆柴の毛色は?
もっともポピュラーな「赤」は茶色に近い毛色で、毛先が赤毛です。「白」はクリーム色に近い白色で、「黒」は黒い毛をベースにところどころ白や赤が入った毛色。
「胡麻」は柴の中では珍しく、赤毛の部分に黒毛が混在しているのが特徴です。
豆柴を飼うときの注意点
お手入れをしっかりしよう
柴の被毛はダブルコートと呼ばれる二重構造になっており、硬くてストレートの上毛と、柔らかな下毛に分かれています。ダブルコートの犬種は抜け毛が多い傾向にあり、換毛期には毛が大量に抜けます。
ブラッシングを毎日おこなうことで毛を取り除き、換毛期はこまめにシャンプーをしましょう。また、ブラッシングをすることで皮膚病にも気がつきやすくなり、犬とのスキンシップができるというメリットもあります。
十分な運動量を確保しよう
散歩の途中にボールやおもちゃで遊ぶ時間も取り入れつつ、体力を思う存分発散させてあげてくださいね。
豆柴がかかりやすい病気
アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎とは、何らかのアレルギーによって皮膚が炎症を起こす症状のこと。アレルギーにはさまざまな種類があり、花粉、ノミやダニ、食物などが原因となります。
アレルギーの症状は、かゆみ、発疹、皮膚の炎症、脱毛、嘔吐、下痢など。もし愛犬が特定の部位をなめたり噛んだりして皮膚が赤くなっていたら、かゆみが出ている可能性があります。
アレルギー性皮膚炎の予防法は?
アレルギーの原因や対策について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
外耳炎
外耳炎とは、耳の穴の鼓膜の外にある「外耳道」に細菌などが感染し、炎症が起きてしまうこと。外耳炎にかかると耳アカが溜まり、炎症がひどいと鼓膜に穴があいたり、腫れや出血が起こり痛みを伴ったりすることもあります。
愛犬が耳や耳の下を何度もかいている、執拗に頭を振っているなどの場合は外耳炎かもしれません。慢性的になると治りにくくなるため、愛犬の様子がおかしいと感じたら動物病院で診てもらいましょう。
ほかにもこんな病気のおそれが
- 緑内障
- 白内障
- 認知症
- 歯周病
しつけをしっかりおこない楽しく暮らそう!
自立しながらも仲良く暮らせる豆柴を育てるには、ほめるしつけを取り入れながら、飼い主さんとの絆を深めていきましょう!
「いぬのきもち」WEB MAGAZINE『柴犬の大きさや理想体重とは?ダイエット法やサークルの選び方も解説』(監修:いぬのきもち相談室獣医師)
「いぬのきもち」WEB MAGAZINE『柴の特徴と性格・価格相場|犬図鑑』(監修:ヤマザキ動物看護大学講師 危機管理学修士 認定動物看護師 ペットグルーミングスペシャリスト 福山貴昭先生)
「いぬのきもち」WEB MAGAZINE『病気・症状データベース(外耳炎)』
「いぬのきもち」WEB MAGAZINE『【獣医師が解説】犬のアレルギー原因と対策|よくあるQ&Aも!』(監修:いぬのきもち相談室獣医師)
監修/いぬのきもち相談室獣医師
文/松本マユ
※写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
UP DATE